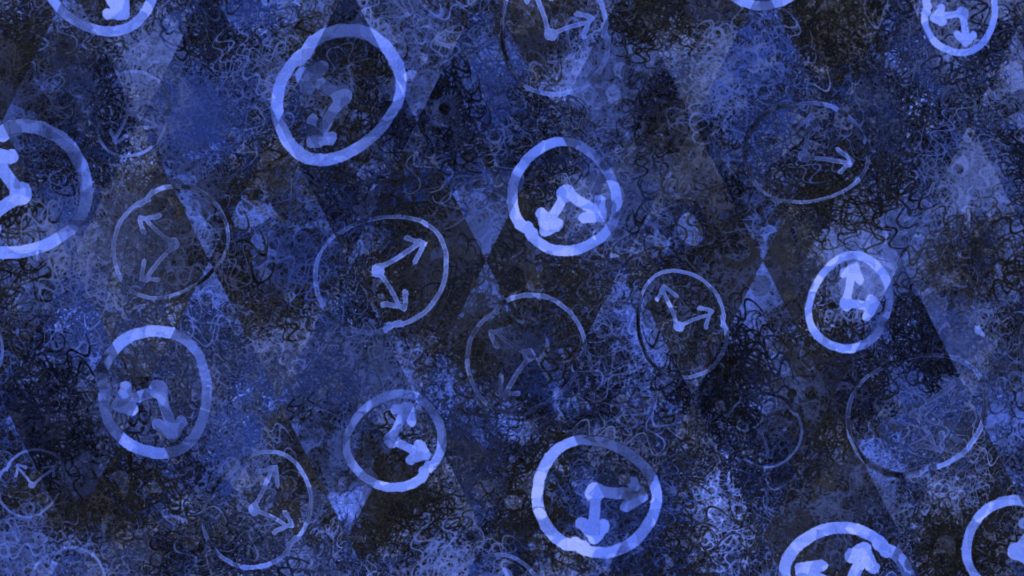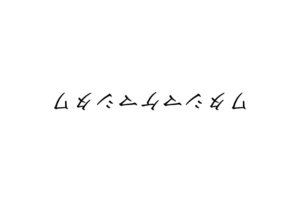仕事には納期がある。しかし執筆者は締め切りを過ぎてから仕事に入る。締め切りを過ぎても、閃きが訪れるのを待っている。時間の中にありつつ時間に服従していない。これは何なのか。
アリストテレスは時間を「前後に関する運動の数」と考えた[1]アリストテレス著、内山勝利他訳『自然学 (新版 アリストテレス全集 第4巻)』岩波書店、2017年、p170(219b1)。。要するに、時計の針が動いた分だけ時間が経過したと言える。ただしこれは時間の経過を運動の数で測定できるということであって、運動そのものが時間だというわけではない。時計は時間を進める道具ではなく、時間の進みを知るための道具なのだ。時間について確かなことは、何の運動もなければ人間に時間の経過を知る術がない、というこの一点に尽きる。だから時間とは「物の運動によって表される何か」としか言えず、時間そのものに関して知った顔で語ることすら許されない。
こうして書くと難しく見えるが、この時間理解は現代社会の中に溶け込み、運用されている。算数の授業で習った、時間と距離と速さの関係を思い出す。「速さ=距離÷時間」、「距離=速さ×時間」、「時間=距離÷速さ」。達成に至るまでの運動の回数を数えるここでの「時間」は、まさに「運動の数」を示していると言えるだろう。その回数によって自らの仕事が完遂されると信じられている数。ただしアリストテレスの場合と異なり、この「時間」は往々にして時間そのものと理解される。時間はもはや間接的に知られる何かではなく、量化された数にされている。この点に関しては時間概念の変容が認められる。
こうして変容した時間概念は更に日常化されて、次のような使い方もされる。人は仕事をするとき、自分の仕事量を大体分かっているので、期限から逆算して一日の労働時間を算出してスケジュールを組む。達成目標を仕事の回数で割って、一回の仕事量を決めている。こうした計画立案は物資の運搬や大工仕事のような物理的・物質的な仕事の場合には問題なく機能する。目的地(距離)を設定し、道路上の速度を確認すれば仕事に要する時間が分かる。建造物(距離)を設定し、作業速度を鑑みれば納期(時間)が分かる。
注目したいのは、スケジュール化されるのはその手の物理的な仕事に限らないという点だ。それは企画を練る、文章を構想するなどといった非物質的な仕事にも適用される。思考という非物質的な行為に上述の「運動」を数え入れるのは厳密に考えれば妙な話ではあるが、しかし日常的にそれは受け入れられている。実際、原稿執筆には締め切りが設定されているし、ものを考えるにも時間がかかる。
ここで「アリストテレスの言う運動に精神活動が含まれるか否か」などという問題に目を奪われないように気を付けたい。そうではなく重要なのは、そうした疑問が容易に思い浮かぶにもかかわらず、なぜ人は日常的にこのようなずさんな概念適用をしてしまえるのか、なぜ精神活動に対しても物理運動を基軸とした空間的時間概念を適用してしまうのか、という点だ。ここには論理の整合性より優先されるべき何かがある。それが何か。
これに関して説得的な議論を展開したいならば、利便性や責任主体性にその答えを求めるべきだろう。それは例えば、原稿執筆の締め切りはその後に続く印刷・運搬などの物理的な仕事にとって便利だから設けられているのだとか、締め切りが設けられることで執筆者の中にそれを守るための道徳的主体性を生み出しているのだ、などという考え方がそれだ。しかしここでは説得的な理屈に力はない。奇妙な理屈で体験を捻じ曲げてこその日記。
なぜ精神活動は時間化されるのか。締め切りの設定やスケジュール化、つまり精神活動の量的時間化はなぜ受け入れられているのか。それは時間を圧倒するためではないか。思索的活動では、閃きや思いつきによって事態が一挙に変わるということがある。むしろ思索とは、アイデアが思い浮かぶその瞬間を待ち続ける仕事だとさえ言いうる。コツコツと時間をかけなければ不可能だったこと(それ故期限内には不可能だったこと)が、閃きによって可能になる。ゆるく適用された「速さ」で揺らぎ「時間」が砕ける。これは物理的な運搬作業ではありえないことだ。距離・速さ・時間の関係は絶対に変えられない。しかし精神活動においてはその関係は崩壊する。運動の回数としての時間は精神活動の数えられなさによってその正体を失う。本来「何か」としか言えない時間を「運動の数」という依り代に封じ込めた上で破壊する。己で人形を壊すように、閃きが時間を打ち倒すという瞬間が訪れる。これが欲しくて私は今日も時間概念を雑に運用し続けている。
関連書籍
注
| ↑1 | アリストテレス著、内山勝利他訳『自然学 (新版 アリストテレス全集 第4巻)』岩波書店、2017年、p170(219b1)。 |
執筆者:S.T.
アイキャッチ画像:image by chenspec