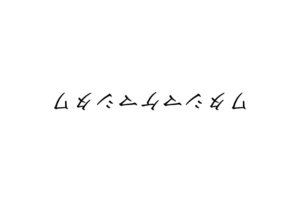※以下物語の核心に触れるネタバレが含まれます。原作未読の方はご注意ください。
※また、読んでいない人にも分かりやすく設定などを折り込むのは面倒、もとい大変だったので、省略しました。興味がある方は是非原作をお読みください。
たとえば、家族や友人、恋人などだれでもいいが、自分の知り合いが仕事をやめると言っていたとしよう。ところが少し経ってから会っても仕事をやめた様子はない。そこでどうして仕事をやめなかったのかを聞いてみるとこんな答えが返ってくる。「もうすぐボーナスがでるので…」。
もしこんな相手に出会ったらどう思うだろうか。もちろん個別の状況や事情があり、相手との関係や個人の考え方によっても判断は異なってくるだろうが、この答えは仕事をやめなかった理由としては一応成立しうるのではないだろうか。その答えを肯定するにせよ否定するにせよ、少なくともそういう判断をする人がいるということは理解できるように思える。
しかし、もしその仕事がかなり危険なもので、命を落とす可能性が高く、実際に多くの同僚がすでに命を失っているとしたらどうだろうか。ボーナスが近かったからという理由は、命を賭してまでその仕事を続ける理由としてはかなり弱い、もしくはかなり異様なもののように思えるのではないだろうか。少なくとも得られる対価に対してあまりにもリスクが高いように思える(もちろんここでもボーナスの具体的な金額や当人の生活状況、家族構成などによって判断が異なってくることは当然だが、ある程度一般的な金額と生活形態を念頭に置いておく)。
■藤本タツキ『チェンソーマン』
さて、このような理由で命にかかわる仕事を続けていたのが藤本タツキの漫画『チェンソーマン』の登場人物である東山コベニ(20)である。コベニはその小柄で大人しそうな外見とは裏腹に、思考と行動がかなり飛んでしまっている人物である。コベニを含む主人公たちの一団が敵の悪魔によって現実世界から隔離された時空間に閉じ込められたとき、主人公であるデンジを食わせろという敵の要求に対し、デンジを殺すべきだと真っ先に主張するのが彼女であり、血の魔人であるパワー(彼女もコベニ、デンジと同じチームの仲間である)がその事件の黒幕であるという自身の説を否定されると、相手を悪魔のスパイだと罵る異様さを持っている。こうした行動は、悪の要求には従わないという通常の少年漫画の原則から外れているだけでなく、コベニが普段は引っ込み思案で自分の意見を言わない人物として描写されているだけにその狂気が一層際立っている(ちなみにデンジを殺すべきと主張するより前に、彼女は錯乱してトイレの水を飲もうとしたために気絶させられている)。
コベニの行動は一貫してどこか狂っていると感じられるが、異様な思考と行動は『チェンソーマン』の主要な登場人物のほぼ全員に共通する特徴である。それもそのはずで、コベニやデンジが所属する「デビルハンター」は、「頭のネジがぶっ飛んでるヤツ」こそ優秀で、「まともなヤツから死んでいく」のである。したがって長く生存し、物語の展開に関わっていくようなキャラは、大なり小なりみな頭がイカレているということになる。
■狂った論理
中でも主人公であるデンジとそのバディ(相方)パワーはとりわけ頭が悪いという設定であり、ふたりの思考と行動がおかしいのはむしろ正常状態である。デンジの場合は小学校にも通えなかったという特殊な事情があるため仕方がない面もあるが、パワーの方は特に理由もなく「ナルシストで、自己中で、虚言癖持ちで、差別主義者」である(とはいえパワーの自分勝手な行動は、嫌いな野菜を人に投げつけたり、好きな食べ物を一人占めしたりといったレベルのものが多く、字面から想像されるような重大な事柄にかかわるわけではない)。そして作中で最強のデビルハンターと言われる岸辺は、そんなデンジとパワーに「頭が終わっておる」と初対面時に言われている。
しかし『チェンソーマン』において登場人物たちが狂っていると感じられるのは、彼らの行動がおかしいからではない。そうではなく、彼らの行動がおかしく思えるのは、むしろ登場人物たちが自分の行動に対して与える理由によってである。死ぬ可能性がかなり高いのに仕事をやめないのは倫理観や正義感からではなくボーナスが近いからであり、敵が闇の悪魔なら、自分の身体に火を付けて光を身に纏ってたたかうのである。『チェンソーマン』のキャラはみな論理的なのだが、その推論のネジがつねに外れているのである。
もちろん自分の考えや行動を正当化するために思考をめぐらせることは、人間だれしもが行うことである。しかし『チェンソーマン』の登場人物の思考はつねに前提から大幅に遠いところへと一気に跳躍してしまう。こうして彼らは、誤った推論が持つ不自然さと狂気をさまざまに体現することになる。
たとえばアメリカからの刺客としてやってくる3人兄弟がいる。彼らは家が壊されたときも死ななかったし、悪魔に飲み込まれても、家が火事になっても、3人で食あたりになったときも死ななかった。こうした経験から彼らが導き出す結論はこうである。「だから俺達は不死身だ」。
もちろんそんなことはない。あげられている事例はたがいに連関がなく、そもそもたんに経験的な出来事にすぎない。無関係の事例をどれほど積み上げたとしても、そこからなにか確固たる結論が導き出されることはない。また、これまでそうだったからといってこれからもずっと同じことが続くわけではないのはだれもが知っていることだ。それは決して論理的な「証明」ではなく、せいぜい個人的なジンクスとでも呼ぶべきものである。しかし彼らにとってはそれが明証的な「証明」なのであり、それを疑う余地はない。だがこの証明を主張していた長男はあっさりと死んでしまい、唯一自分たちの死の可能性を考慮していた三男だけが死をまぬかれる。
主人公のバディであるパワーにいたっては、自分に都合の悪い記憶を改竄してしまうという癖を持っている。だからこそパワーは虚言癖持ちとも言われるのだが、こうして彼女はつねに自分にとって都合のいい物語を作りだすのであり、そこで生じる現実と彼女の認識とのずれが『チェンソーマン』に悲喜こもごもの笑いをもたらしてくれる。
■論理的思考を超えて
ところで、ほとんど論理狂とも言える『チェンソーマン』の登場人物たちだが、彼らが自分の論理的判断に従わない場面がひとつだけある。それが物語の終盤においてパワーがマキマを裏切る場面である。「支配の悪魔」であるマキマは、味方を装っていたが、実際にはすべての出来事の黒幕だった。攻撃が通じず、ほとんど不死身で、自分より格下の相手を支配する能力を持つマキマは、作中でもおそらく最強の存在である。そのマキマによってパワーは一度殺されてしまうのだが、デンジを救うために復活する。ところがパワーは、せっかく復活してきたにもかかわらず、マキマに勝てないと悟るやいなやあっさりとマキマに寝返ってしまうのである。この変わり身の早さと身勝手な行動がパワーの一貫した特徴でもあるのだが、しかし一度寝返った後、またすぐにパワーはマキマに逆らうことになる。そしてパワー自身、「絶対勝てないのに」なぜ逆らってしまったのかと泣きながら自問するのである。
まさにこの一点、主人公デンジのバディであるパワーが、みずからの論理的思考を理由もわからずに超えてデンジを助けようとする一点において、『チェンソーマン』はとりわけ少年漫画たりえている。思えば主人公のデンジは小学校にも通えず、「普通の生活」をすることが最大の希望であり、彼の行動原理はきわめて即物的かつ欲望に忠実である。普通の食事、ベッドでの睡眠、そして性欲。彼の行動は明快で、それはほとんどつねに少年漫画のセオリーの真逆をいく。「ナルシストで、自己中で、虚言癖持ちで、差別主義者」であるパワーもまた、物事をつねに自分の都合のよいように考え、実際に行動に移す。物語の序盤では主人公をおいて逃げることさえあり、その言い訳は、逃げたのではなく「お腹が空いたから帰っただけ」である。
とても『週刊少年ジャンプ』で連載されているとは思えない設定と行動であるにもかかわらず、それでもジャンプ漫画として成立しているという印象があるとすれば、それは物語の佳境であるこの場面に負うところが大きいのではないだろうか。つねに自分の都合のよい論理を作りだすパワーが、主人公のために、それも自分でもわからないままに自分の論理的な思考を裏切ってしまい、なおかつそれがデンジが「初めてできた友達」だからだと語るとき、そこで一気にデンジとパワーのあいだの特別な関係が前景化してくることになるのである。それを「友情」と呼ぶこともできるだろうが、そこにみられるのはスポーツ漫画におけるチームの絆やバトル漫画における仲間意識ともまた違った友情であり、人と魔人、男と女という種族や性別を超えた関係である。このことがデンジとパワーの関係を一層独特の形容しがたいものにするとともに、『チェンソーマン』という作品自体を立体的で奥行きのあるものにしている[1]ちなみに、キャラに立体的な奥行きがまったくなく、ほとんどただの記号と化してしまっているのが尾田栄一郎の『ONE PIECE』である。。
振り返れば、デンジとパワーの関係が決して性的/恋愛的なものではないことはかなり序盤から幾度か描かれていた。そして女とデートすること、キスやセックスすることを夢に描いていたデンジが、パワーに対して欲情しない自分に気が付くとき、ふたりの関係がそれらとは違ったものであることが明確なものとなるのである。実のところデンジとパワーの関係もマキマによって仕組まれたものであることが示されているが、そうであればこそ、マキマはみずからが作ったはずのデンジとパワーの関係によって最終的に負けることにもなる。ここには「支配の悪魔」であるマキマですら支配することのできなかった特別な関係がある。
人間とは「ロゴスを持つ動物ζῷον λόγον ἔχων」だというアリストテレスの有名な言葉があるが、ロゴスすなわち論理や理性は完全無欠ではない。それはつねに不条理さや誤った使用法を伴っているのであり、『チェンソーマン』はロゴスの持つ不完全さやその不条理な帰結を示してくれるだけでなく、それを超えていく契機をも垣間見せてくれるのである。そしてそれはまた少年漫画というものが持つ特質のひとつなのかもしれない。
関連書籍
注
| ↑1 | ちなみに、キャラに立体的な奥行きがまったくなく、ほとんどただの記号と化してしまっているのが尾田栄一郎の『ONE PIECE』である。 |
執筆者:渡辺洋平
アイキャッチ画像:エドワード・フォン・ロングス(Edward von Lõngus)《 エストニア風スティック・ダンスStick dance Estonian style》2017年、タリン(Photo by Külli Kittus)